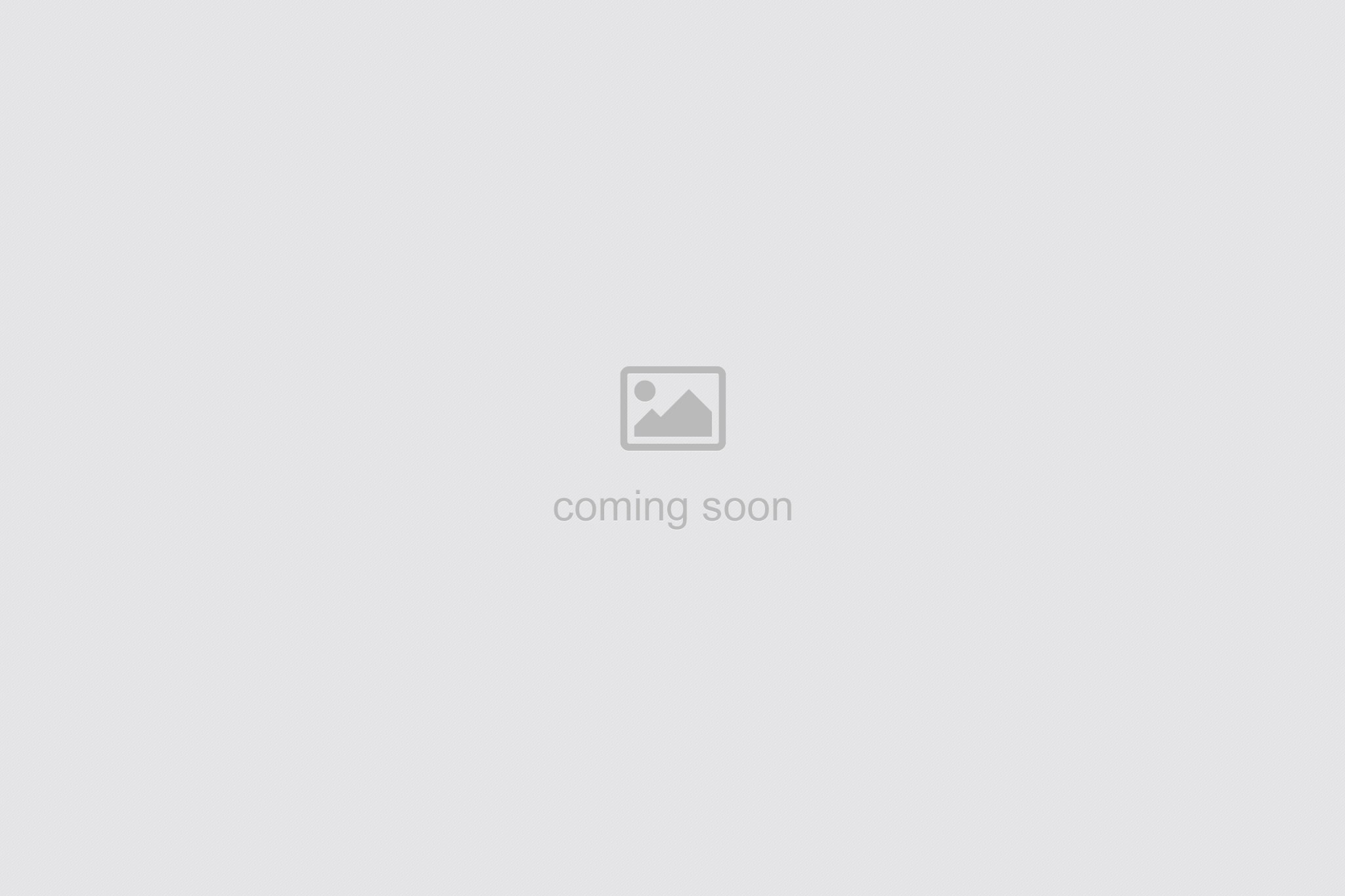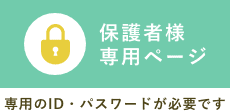ひとりごと…
今日の出来事
サッカーフェスティバル
2019-03-04
3月2日(土)養精中学校でサッカーフェスティバルが行われました。茨木市内の私立保育園・認定こども園30数ヶ園が参加し、820名のこども達がサッカーを通して交流を深めました。らいおん組のこども達も、日頃の練習の成果を十分に発揮し、男児の部では準優勝を果たしました。どのチームも一生懸命で、試合に臨むこども達一人ひとりの真剣な表情に成長を感じ、深く感動しました。試合に負けて悔し泣きをするこども達やその姿を見て一緒に目頭を熱くする保護者の方々や先生たちの姿。どの場面もキラキラ輝いて見えました。久しぶりのトロフィーは、しばらくらいおん組のお部屋に飾った後、玄関に飾ろうと思います。
「らいおん組のみんな、とってもカッコよかったよ!たくさんの感動をありがとう!!準優勝おめでとう 」
」
園内研修会
2019-01-10
今日の研修では、一人ひとりの子どもたちの力を伸ばし、子どもたちがしっかり遊び込めるような環境にするにはどうすればいいのか?また、天王こども園が居心地の良い場所となるには私たちがどうすればいいのかなどを振り返りながら考える機会となりました。どの職員も真剣な面持ちで話し合っていました。みんなの保育にかける熱い情熱を感じた研修となりました。
防犯訓練
2018-12-21
12月17日(月)職員対象の防犯訓練がありました。茨木警察 生活安全課の方に指導いただき、本番差ながらの緊迫した雰囲気の中で行いました。最近、子どもを取り巻く色々な事件の情報が報道を通じて入り、安全に生活するためにはどうすればいいのかという不安も感じます。子どもたちを守るためにはどうすればいいのかを考える良い機会になりました。今後も訓練で学んだ事や、これからの課題などについて職員で話し合いながら、危機管理について考えて行きたいと思います。
台風21号 恐るべし!
2018-09-05
おはようございます。昨日の台風上陸から一夜明け、その被害の大きさに驚いていますが、皆様はいかがでしたでしょうか?
こんなに大きな台風は、気象予報士の片平さんのツイートによると、57年ぶりの記録的な暴風だそうで、その威力の凄さを目の当たりにして恐怖を感じた方も多かったと思います。こども達は元気に登園しいつもの園生活に戻っています。6月の地震に始まり、大雨、台風とこの数ヶ月で経験した事の無い、自然災害の恐怖を味わいました。命があっただけ良かったとはいえ、この恐怖感は子どもたちの心にも大きく残っている事でしょう。子どもたちの心のケアーも含め、園生活を充実した日々になるよう、職員一同きめ細やかな保育を提供して行きたいと思います。また、お子様の様子で気になることがございましたら、職員までご相談ください。
園長 八反田 由美